「AIが世界を変える」といった言葉を聞くようになって久しいが、実際の社会変革はどれほど進んでいるのだろうか。「AI」という言葉だけが独り歩きし、実態が伴っていないケースも散見されるように思える。
一方で、バズワードに流されず、着々と社会実装を進めているプレイヤーもいる。「ヒトとAIの共生環境の実現」を目指し、AIソリューション事業を展開するギリアもその一社だ。ディープラーニングソフトウェアの開発などを手がけていたUEIとソニーコンピュータサイエンス研究所の合弁として2017年6月に設立された同社は、2020年4月、グロービス・キャピタル・パートナーズ(以下、GCP)を引受先とする第三者割当増資、同10月には農林中央金庫を含めた4社からの第三者割当増資を実施した。
AIビジネスの最前線、そして大企業とスタートアップによる合弁会社ならではの組織力を武器に変革を進めるギリアの勝算を、同社の投資担当を務めるGCPのキャピタリスト・南良平、元UEI代表取締役社長でありギリアで代表取締役社長兼CEOを務める清水亮氏、ソニーコンピュータサイエンス研究所で新規事業創出プロジェクトを手掛けたのちギリアの取締役副社長兼COOに就任した齋藤真氏に聞いた。
(取材・構成:鷲尾 諒太郎 撮影:栗村智弘 編集:小池 真幸 )
“囲碁で勝てること”こそが、AIの本当の価値
──清水さんはビジネスにおけるAI活用の現在地を、どのように見ていますか?
 ギリア株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 清水亮氏
ギリア株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 清水亮氏
新潟県長岡市生まれ。プログラマーとして世界を放浪した末、2017年にソニーCSL、WiLと共にギリア株式会社を設立、「ヒトとAIの共生環境」の構築に情熱を捧げる。東京大学大学院情報学環 暦本研究室 客員研究員。主な著書に「増補版-教養としてのプログラミング講座 (中央公論新社)」「よくわかる人工知能 (KADOKAWA)」「プログラミングバカ一代 (晶文社)」など。
清水:インターネット黎明期のような状況だと感じています。私は1994年に大学に入学したのですが、当時はまさにインターネット黎明期でした。「インターネットを使ったビジネスをします」という会社が次々と現れてきた一方、急速な社会変革に対して懐疑的な見方をしている人も少なくなかった。昨今のAIも、似たような状況なのではないでしょうか。
ただし、AIが世界を大きく変えうることはたしかです。なぜなら、AIは人の代わりに、あるいは人以上に的確な判断を下せる存在だからです。これまで世界中のAIに関する学会に参加してきましたが、実は参加者たちを最も驚かせているのは、画像から犬や猫を判別できることではなく、囲碁で勝てること。勝負に勝てるとはすなわち、その局面の状況を分析し、判断し、戦略を立てられるということです。
これまでビジネスに限らず、最終的な決断を下す主体は、唯一の“知能的存在”である「人」でした。しかし、AIの登場によって、大きく状況は変わりつつある。たとえば、P/LやB/Sなどを見て経営的な判断を下すことは、AIにも可能です。むしろ、大量のデータを学習させることで、人よりも正確な判断を導き出せる。これまで人にしかできないとされてきた、多様な情報を分析し然るべき判断を下す営みを代替できるからこそ、AIは世界を大きく変えうるのだと考えています。
 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ シニア・アソシエイト 南良平
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ シニア・アソシエイト 南良平
前職である大和証券にて未上場企業に対するIPOアドバイザリーや、主に電機セクターの上場企業に対するファイナンスやM&A等の提案及び執行サポートに従事。2018年1月、グロービス・キャピタル・パートナーズ入社。慶応義塾大学経済学部卒、米国カルフォルニア大学バークレー校MBA修了。
南:AIの社会実装が進み、社会を大きく変えていくのは、不可逆的な流れだと考えています。これからがまさに本番といったフェーズで、市場としてもさらに拡大していくでしょうし、大きなポテンシャルを秘めていると捉えています。
一方で、AIの社会実装を進められる人材はまだまだ足りていません。ビジネスの現場にAIを落とし込むことは、簡単なことではない。カスタマイズなしに顧客に提供できるものではないので、丁寧に顧客の要望を聞き、それに応じたソリューションを提供していかなければならない。AIに関する知識はもちろん、深いビジネス理解も必要になる。社会実装を推進できる人材の確保が、業界全体の課題になると考えています。
AI化は、まずB2Bから始まる
──成長が不可避なAIマーケットにおいて、ギリアが展開している事業についてお伺いします。現在はB2B事業に注力されているそうですね。
齋藤:はい。ソニーでの経験に鑑みても、新しい技術の社会実装は、まずビジネスで活用されることから始まり、徐々にコンシューマーに広がっていくプロセスをたどることが多い印象を持っています。たとえば、家庭用ハンディカメラは、もともと放送局のために開発された技術から生まれたものです。
さらに、AIを活用することで、導入企業の業務プロセスを変え、その先の業界構造をも変化させていきたいと考えています。たとえば、『家庭教師のトライ』を展開するトライグループ様と共同で開発した「トライ式AI学習診断」と「入試問題的中AI」。AI学習診断とは、生徒の能力把握を目的としたシステムです。10分程度の簡単な診断テストを受けてもらうことで、生徒それぞれの得意不得意を分析し、「どの教科のどの単元を学習すれば、効率よく成績を伸ばせるのか」を明確にします。トライグループ様に限らず、多くの教育系サービスを展開する企業は、数時間ほどかかるテストを通じて生徒の能力を把握していました。また、そのテスト結果を見て弱点を判断するのは、各教室の先生。すなわち、属人的な判断に頼らざるを得なかった。この業務をAIに代替させることで、効率良く、正確な診断を下せるようになりました。
そして、AI学習診断が示した弱点を克服するための一つのケースとして、「どのような問題を解くべきか」を導き出すのが、入試問題的中AIです。たとえば、ある生徒が志望大学に合格するためには「数学のこの単元の、こういった問題を練習すべきだ」といったことを示し、問題集を作成します。生徒の学力診断から、合格に至るまでの道筋の提案までをAIがサポートすることで、先生たちが担う役割は大きく変化し、より効率的な指導が可能になりますよね。これらの導入が進めば、教育のあり方を大きく変えられると思っています。
──導入企業の業務プロセスを変革していくうえで、どういった点がポイントになるのでしょう?
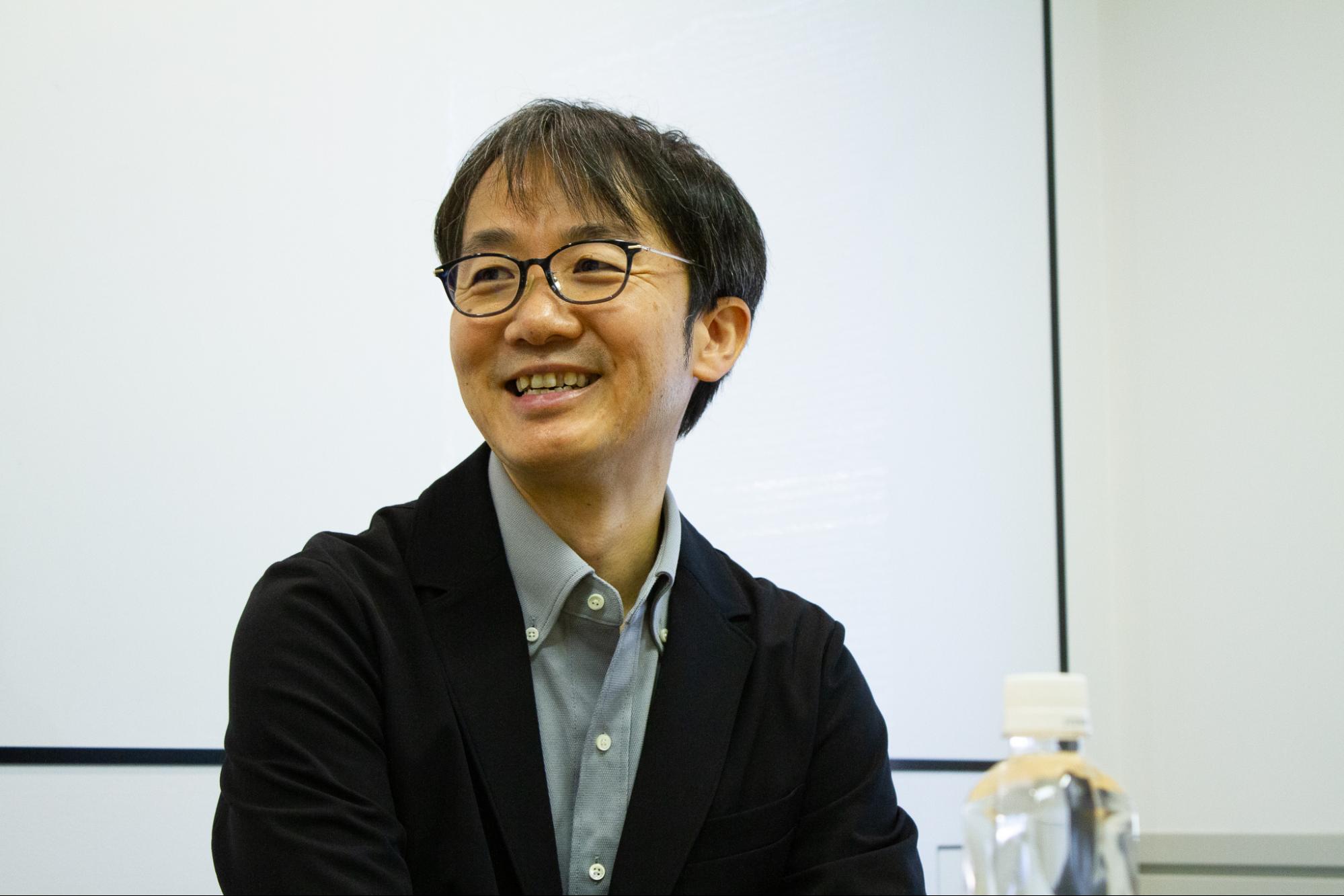 ギリア株式会社 取締役副社長 兼 COO 齋藤真氏
ギリア株式会社 取締役副社長 兼 COO 齋藤真氏
1991年ソニー株式会社に入社。半導体エンジニアとして10年間キャリアを積んだ後、技術戦略スタッフに転身、ソニー全社の技術戦略立案などを担当。2012年よりソニーコンピュータサイエンス研究所に出向。新規事業創出プロジェクトを担当、株式会社ソニーグローバルエデュケーション(2015年)、ギリア株式会社(2017年)の設立を主導し、両社の経営陣として参画(現職)。
齋藤:「業務プロセスをどのように変えたいのか」「変化させるためにはどのようなデータが必要なのか」を見極めることが重要です。アルゴリズム自体は、すでにさまざまなタイプのものが世の中で公開されているので、データの品質が勝敗を分けます。プロジェクトの開始時、クライアントのバリューチェーンの中にはどんな業務があり、それぞれの業務の中でどのようなデータが生み出されるのか、そして業務をどのように変えていきたいのかをヒアリングしていきます。
運が良ければ、すでにクライアントが保有しているデータだけで対応できますが、不十分な場合もあります。たとえば、トライグループ様との取り組みでは、AI学習診断の構想自体は早い段階で見えたものの、その時点で保有しているデータだけでは実現が難しそうだと分かりました。そうした場合には、「どのようなデータを」「どれだけ集めるべきか」を提案し、データを集めるサポートをします。トライグループ様との取り組みでは、数万人の生徒にトライグループ様が作成したテストを受けてもらい、AI学習診断を構築するためのデータを集めました。
顧客の利益を生まないAI導入に意味はない
──かなり上流の部分から、AI活用をサポートされているのですね。
齋藤:それがギリアの特長だと思っています。最初にクライアントとお話しする段階から、営業だけではなくエンジニアも同席するようにしていまして。夢物語は語らず、プロジェクトの初期から「できること」と「できないこと」を明確にし、クライアントのニーズを満たすためには何から始めるべきなのかを、技術的な側面からもアセスメントできる体制にしています。

清水:既存のシステムを持っていき、「これを使ってください」と押し付ける売り方はしていません。業務のどの部分をAI化すれば最も付加価値を生むことができるのか、クライアントに寄り添い、共に考えることを大切にしています。トライグループ様との事例でいえば、AI学習診断と入試問題的中AIによって生徒の成績を効率よく上げることができれば、新規会員の獲得にもつながりますし、月謝もアップできるかもしれないと考えました。結局はAIによって、いかにクライアントに付加価値を提供するのかが大切なのです。
「お金を出してくれたら何でもやりますよ」といったスタンスは取りません。私たちが手がけるのは、クライアントやクライアントが属する業界に価値を提供し続けられる可能性が高いプロジェクトのみ。顧客にとっての価値、すなわち利益を生んでナンボだと思っています。
類似事業を展開している企業の中には、PoC(概念実証)までしか手掛けない企業も存在します。たしかにPoCだけでも短期的な売上は確保できますが、本当の意味で顧客の利益につながっているとは言えません。AIを活用して事業を変えられる可能性があることを示すだけではなく、継続的にサポートをして事業を変革し、利益につなげるところまで徹底して伴走する点が、私たちの特長です。
齋藤:B2Bビジネスの本質は「クライアントに儲けてもらうこと」。業務が効率化されるだけではダメということです。メンバーにも顧客の利益につながる提案をするよう、常に言い聞かせてきましたし、その意識はかなり定着してきたのではないかと感じています。
南:ギリアには、技術とビジネスの観点を両方踏まえ、AIの社会実装を進められる人材が揃っています。案件の性質上、なかなか詳らかにできないのが悩ましいですが、私たちがギリアから最初にお話を聞いた時点で、継続的にフィーを得られる状態になっている案件をいくつも持っていました。提案力や実行力を兼ね備え、AIの社会実装を進められるチームをつくれていると感じました。ソニーグループで働く優秀な人材が、自ら希望してギリアに加わっていることもユニークでしょうね。人材の供給源を確保できていることが、最大の強みになっていると思います。
“勘”に頼った経営を脱するため、大企業との提携が必要だった
──清水さんが代表を務めていたUEIとソニーコンピュータサイエンス研究所による合弁会社というかたちを取ることにしたのは、なぜでしょう?

齋藤:ソニーとしては、自社だけではできないことを成し遂げるために、手を組むことを決めました。ソニーグループは、新たな事業を立ち上げるためにチャレンジを繰り返していました。たとえば、新規事業の一環として、ソニーグローバルエデュケーションという教育事業を展開する会社を立ち上げ、私は2015年から取締役を務めています。この会社はソニーが単独で立ち上げたもので、メンバーはソニーグループからの出向者が中心です。
ただ、ソニーの“正攻法”に縛られてしまうという問題も抱えていました。もちろん、ソニー出身者だからこそうまくいくこともあるのですが、そうではない部分もある。みんな同じ文化圏でキャリアを積み、同じ教育を受けてきたからこそ、発想も似通ってくる。内部の人間だけでインキュベーションをするのは限界があると感じていました。
外部の企業と手を組むことで、この停滞した状況を打破したいと考え、インキュベーションプログラムを立ち上げました。その一環として清水が率いるUEIと手を組んだことが、ギリア設立のきっかけになっています。
清水:ソニーコンピュータサイエンス研究所から声がかかったのは、「自力ではこれ以上会社を大きくできないな」と限界を感じていたタイミングでした。UEIを14年ほど経営してきた中で、自分が20人以上の組織をマネジメントできないと気づいたのです。私は大きな組織でマネジメントのスキルを学んだこともなく、いわば勘だけでやってきたため、直属の部下が20人を超え、会社全体で130人くら
そんな中で、「一度、思いっきりやりたいことをやってみよう。将来的には受託開発の案件獲得につながればいいな」と思ってつくったのが、手書き入力に特化したタブレット『enchantMOON』でした。これに興味を持ってくれた複数の会社が「一緒になにかやれないか」と声をかけてくれた。その1社がソニーコンピュータサイエンス研究所でした。繰り返しになりますが、自分の力だけではこれ以上会社を大きくできないのではないかと思っていたタイミングだったので、話を聞いてみようと。
──複数社から協業の打診があった中で、なぜソニーを選んだのでしょうか?
清水:1つ目の理由は、信頼できる人がいたことです。ギリアの取締役会長であり、ソニーコンピュータサイエンス研究所の代表取締役社長でもある北野と齋藤から声をかけてもらったのですが、プロジェクト初年度はたいしたお金を出してくれなかった。「この額でどうしろと?」と思いましたよ(笑)。
でも、齋藤に「来年度は少なくとも100倍の予算が必要だ」と伝えると、「分かった」と言って実現してくれました。社内での承認を得なければなりませんし、100倍の予算を取ってくるのは簡単ではないはずですよね。それでも、北野と齋藤は約束を守ってくれました。この人たちは信頼できると感じ、手を組むならこの人たちだなと。
2つ目の理由は、ソニーがグローバルで戦える数少ない日本企業だと考えていたからです。日本企業が海外の会社を買収することはよくありますが、うまくいかないことが多い。日本企業に買収された会社を何社か訪ねたことがあるのですが、向こうからすると「よく知らない日本の企業に買収された」といった認識のようなのです。そうすると「聞いたこともない日本企業の傘下でなんか働きたくない」と、中枢を担っていた人が辞めてしまうところを実際に見たことがありました。
ただ、同じタイミングでソニーが買収したサンフランシスコの会社を訪ねてみたら、その会社からは人が抜けていなかった。なぜかといえば「あのソニーが俺たちを認めてくれたんだ」と、買収されたことを誇りに感じているから。社内はとてもいい雰囲気でしたし、むしろ買収を契機に人が増えているほどでした。海外のマーケットにおいて、これほどのプレゼンスがある日本企業は多くありません。力を借りない手はないじゃないですか(笑)。
「1,000億円の売上高を目指す」が当たり前の環境
──大企業とスタートアップが手を組むことで、どういった価値が生み出せるのでしょう?
齋藤:長期的な視野で、新たな技術の社会実装に取り組めるようになります。ソニーという基盤があるからこそ、短期的な利益を追求するのではなく、腰を据えてAIの社会実装に取り組める。ギリアを100年、200年続く会社にしたいと思っていますし、それを実現できる可能性は十分にあると思っています。

清水:ソニーの人たちは、とても視座が高い。彼らの成功の基準は、ウォークマンやプレイステーションです。普通のスタートアップでは考えられないほど高い目標設定がデフォルトになっている。スタートアップとは全く違った物差しを持って仕事をしているなと感じました。
──高い目標を目指すことが当然の環境は、大企業との合弁会社ならではですね。その他に、組織として特徴的な部分はありますか?
齋藤:組織運営に関しては、ソニーでの経験が活きています。大企業の強みは、組織力の高さです。多くのスタートアップは役職者の権限が曖昧だったり、組織としてのルールが定まっていない部分があったりすると思うのですが、ギリアでは明確な組織運営上のルールを設けています。たとえば「課長が責任を持つのはここからここまで」といったように、役職者ごとの職責を明確にすることで、マネジメントがしっかりと機能する仕組みを整えています。
また、先ほど南さんから優秀な人材の確保が重要といったお話がありましたが、採用はもちろん、育成にも力を入れています。未経験の人でも力をつけ、活躍するための制度も整えて、飛び抜けた個人の力に依存せずとも事業を伸ばせる組織をつくり上げたいと思っています。
──メリットがある一方、会社としての規模や風土が全く異なる会社が協業するからこその苦労もあったのではないでしょうか。
清水:もちろんです。これまで私はすべての最終的な判断を自分で下していましたが、権限移譲を進めたことで、その範囲も限定されました。以前と比べて90%ほど、やることが減ってしまった感覚がありましたね。
齋藤:スタートアップの強みはスピード感ですよね。社長が「OK」と言えば、すべてのことが前に進みはじめる。でも、組織をちゃんとつくっていくためには、すべての決裁を社長に任せるのではなく、権限委譲を進めなくてはならない。いくら清水でも、担当範囲を超えて指示を出すことはできないのだと理解してもらうのには、時間がかかりましたね(笑)。「越権を許してしまうと、組織が崩壊してしまうんだ」ということを、繰り返し伝えていました。
従来のソニーはハードウェアが中心の会社だったので、スピード感がないように見えてしまうのは仕方ないかなと思いました。試作品をつくるだけで10億円から20億円かかるので、判断も慎重にしなければならず、すぐにGOサインは出ません。でも、ソフトウェアの会社はそうではない。後から修正することを前提に、「とりあえずつくってみよう」と動き出す。この感覚の違いを解消することには苦労しましたね。現在は、ソニーからの出向者におけるソフトウェア開発の経験者の割合も増やし、決裁スピードに関する感覚は合ってきていると思います。
B2BからB2Cへ──すべての人がAIの価値を享受できる社会をつくる
──組織力を向上させた先に、今後はどのようなチャレンジに打って出る予定でしょうか?
齋藤:B2B事業においては、トライグループ様のプロジェクトのように、クライアントの業務プロセスを根幹から変えていくような事例をもっと生み出していきたいです。

清水:B2B事業でつくった原資は、B2C事業に投資していきます。具体的には、2つの方向を検討しています。一つは、『Google』のようにフリーで誰でも使えるようなサービス。もう一つは、『Photoshop』のようにユーザーは限定されるものの、高額で高い付加価値を提供するサービス。後者は以前から取り組んでいますが、AIの知見がないユーザーでも簡単に使えて、価値を享受できるレベルには至っていません。
より多くのユーザーに価値を提供できるプロダクトを生み出せるよう、チャレンジしていきます。来年初頭にはローンチする予定で進めていたのですが、新型コロナウイルスの影響もあり、予定を変更せざるを得ない状況です。社会全体の価値観が大きく変化しようとしているので、その変化をしっかりと捉えたうえで、事業に落とし込んでいきたい。
──南さんは、これからのギリアにどのようなことを期待していますか?
南:短期的には、AIを社会実装するカタリストとしての役割を期待したいです。それができるプレイヤーだと思っています。中長期的には、他のAI関連企業との比較の中で、どういったメッセージを世の中に発して、どんな会社として認知をされ、どのようにスケールしていくかが重要になってくるでしょうね。その点はこの先、引き続き検討が必要だと思っているので、一緒に議論していきたいです。
さらに長期的な目線で言えば、先ほど清水さんがおっしゃっていたように、B2BとB2Cの両面から事業を進め、AIがより一般的になっている世界を実現してもらいたい。大きく社会を変えるようなチャレンジに、期待しています。

(了)
